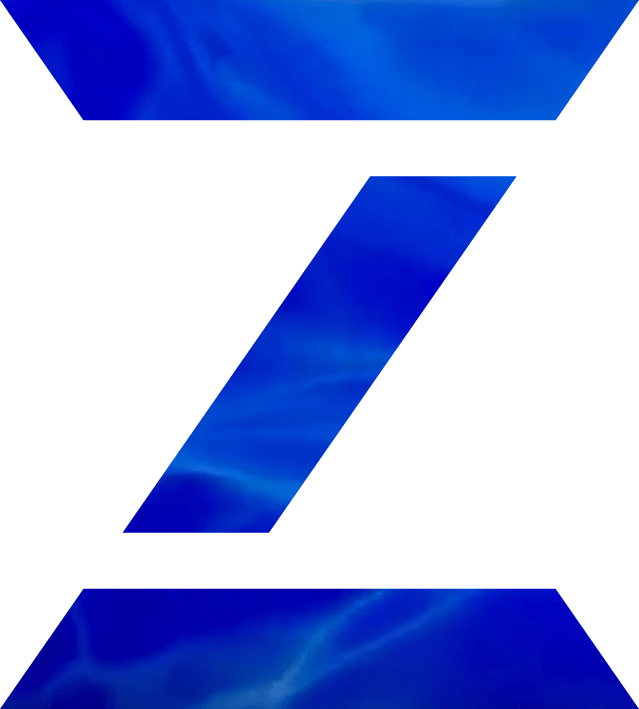仕事は、仕事の前にできている
「いい仕事をしよう」と
思う人より、
「いい準備をしよう」と
思う人のほうが結果がでる。
成功しているYoutuberは
「いい準備」に余念がない。
考え方の、考え方
デザイン会社に勤めていた時代、
「社長をどう支えていくべきでしょうか?」
と、ある経営者に聞いたことがある。
返ってきた応えは
「そう思う時点でダメなんだ。
君が、この会社を買収しようと思わなきゃ」
だった。
飛躍した高みを望み
はじめて目の前の小さな目的を達成できる。
給料が安い、安い、と嘆く前に
突き抜けた成果を上げないと
1000円すらあがらない。
突き抜けて目立たないと
給料の上がる理由が作られない。
ヒット商品を目指さない
ヒット商品とは乱気流のようなもので、
大きく上がれば下がりやすく
そのブランドの回復には
2倍の資源を要する。
それよりも、
その商品があたりまえの存在になるよう
インフラ化を目指し、
浸透と同時に価値(=価格)も上げていく。
これは、組織で働くスタッフのあり方も
同じである。
ステルス・マネジメント
経営者が持つ権利・権威に
暗い部分が見えると
従業員はロイヤルティを無くしやすい。
一時期、広告に見せない広告手法として
ステマ(ステルス・マーケティング)があったが、
経営手法にもステマ(ステルス・マネジメント)があると思う。
「うちの社長はステマだから」。
と、従業員の信頼を失わないよう
気をつけなければならない。
だれもが調べ・発信できる透明化の時代に、
経営者が持つブラックボックスは
すでに機能していない。
「俺は苦労したんだから、これくらいは当然だ」
という考え方は前時代となった。
顧客を愛するか。上司を愛するか。
上司は、部下の能力が上がると警戒する。
ポジションを奪われる前に
手を打とうとする。
顧客は、担当の能力が上がると喜ぶ。
さらに良いサービスを受けられると
期待してくれる。
真に愛すべきはどちらか。
自分を頼り
長く仕事を任せてくれるのはどちらか。
自ずと見えてくる。