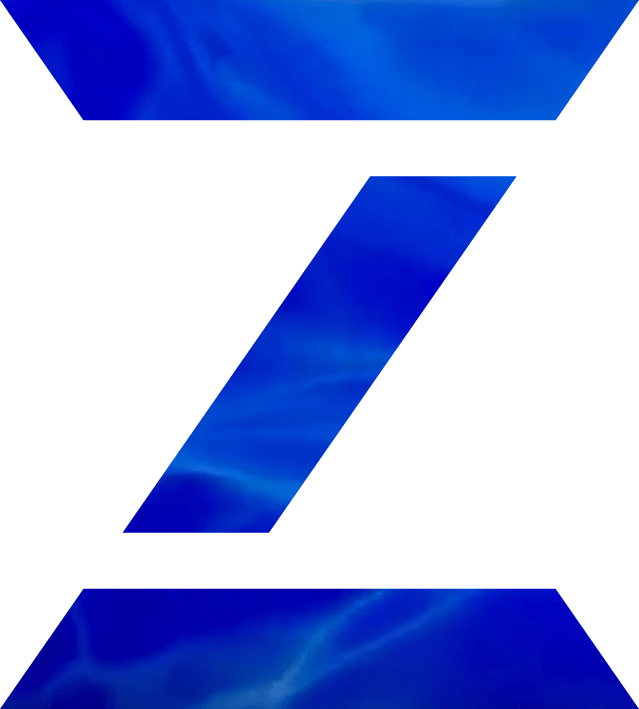小欲より大欲
かっこいいものを
買えるより
かっこいいものを
つくれたほうが
かっこいい
雨で、涙が濡れている
彼が、その景色を見たのは
まだ2歳の頃で
とおく、ながい廊下の奥には
粗末なこしらえの階段が
離れへと伸びている。
視点が低いせいか傾斜がこわく、
後ろから追ってきた祖父に
ひし、としがみついては
袖をよく濡らしていた。
園庭の緑には残光がある。
いまも、一葉一葉を
丹念にぬぐう老境の姿があるようで
ひ孫らも一人を除いて
おなじ景色を見ていた。
皐月の空は
悲しいほど青く晴れているのに
雨だけが、何故か
泣いているように見えた。
売る前に買う
100万円の商品を売りたければ
100万円の商品を買ったことが
なければならない。
100万円の商品を
買う人の気持ちを
わからなければいけない。
高級品を買う人は
財布の中身を見て決めていない。
高級品を買う人は
気分で決める。
買い手の気分は
売り手の共感量に比例する。
進め方より考え方
仕事という行為に
1から10があるとすれば、
0を大切にする。
1から10の精度は
0が決定する。
商人より職人でありたい
数字を、仕事で追いかけるのが商人。
仕事に、数字を追いかけさせるのが職人。
一流のメジャーリーガーは
「自分のスイングができれば
数字はついてくる」と言う。
仕事に、数字を追いかけさせている。
数字ありきの人間ほど
素振りも、修行もしない。
仕事に、数字を追いかけさせる
職人でありたい。